THEアロエ栽培ver.3
THEアロエ栽培ver.3SINCE 21/Sep/1996
 |
<アロエ知りたいメニュー> |
| アロエの育て方 | |
| アロエの植え替え方 | |
| アロエの株分け | |
| 日々の世話 | |
| アロエの使い方 乾燥葉,アロエ酒、アロエ,料理、アロエ化粧水、アロエ風呂。アロエ刺身 |
|
| アロエの由来、種類 | |
| アロエ栽培農園 | |
| 世界のアロエの花 | |
| ご質問、ご意見などはこちら | |
| アロエの通販 通信販売のページ |
|
| ■ホームへ■ |
| 天の星錦:一般的に花数の多いアロエにあって、ちらほらと花がつくこれは珍しい部類と言えます。 梅雨明け後は気温もかなり高い状態が続きます。雨も少なくなるので、水枯れが心配、、という方もおられるかとは思います。 キダチアロエ、アロエベラの場合には強力な保湿機能を備えているので、半年程度の渇水でも枯死に至ることはほとんどありません。 気温が高いときは水やりをするときに、日中炎天下を避けることを留意しましょう。 アロエの中心部に水が溜まった状態で炎天下に晒すと、アロエの芯が煮えてしまう場合があります。 夏場は水もすぐ蒸発してしまうので、毎日水やりしてやってもいいのですが、鉢植えの場合、基本は、早朝か夕方です。 二〜三日に一度から週一くらいで適当かと思います。常時土が湿った状態はアロエは嫌がるので加減してください。 自主的にアロエ農園及び近隣地域の放射線量測定うを行いました。:結果はこちら。 |
[インデックスへ戻る]/[アロエ栽培農園]/[アロエ実験温室]/[製品案内]/[アロエの里ではアロエの花まつり]
[お問合せ、ご意見]
ここはアロエの栽培の様子を含め使い方を紹介します。随時加筆しています。
<<アロエの由来・種類>> 原産地:日本ではなじみが深いキダチアロは南アフリカ共和国、アロエベラは北アフリカからアラビア半島にかけて、原種は一説には地中海との説もあります。 種の全体としては南アフリカ、マダガスカル、東南アフリカ、等に集中している多肉植物・学術的な分類ではユリ科アロエ属 アロエ属:ユリ科アロエ属は原種としては400種前後、細分化すると500種を超える種類があります。 ごく限られた個体数しかないアロエもあり、現在はアロエ属全種がワシントン条約により保護され(アロエベラを除く)、加えて一部は各国国内法により厳しく輸出入が制限されるほど貴重な植物とされています。 私達はアロエを栽培する傍ら、アロエの収集もしていて、原種保存のために温室をつくりました。鉢植えのイメージがあるアロエですが実際には中-大型種が多く数mになるものも珍しくありません。 アロエという名前:語源はアラビア語のロエ(苦いという意味)で、これを音写で蘆薈(ろかい)となり、日本へ渡来した当時は「蘆薈(ろかい)」と呼ばれていました。苗木の状態ではなく、もともとはアロエ原液を煮詰めた樹脂の形で入ってきたとも言われています。 ルーツでもある南アフリカではコインの図柄にも使われるほど現地では馴染みの深い植物のようです。 アロエの名前というのは実は通称で呼ばれている事が多く、 日本でよく耳にするキダチアロエは木のように立つアロエなのでキダチアロエという通り名が広まっています。原種名はアロエ・アルボレセンスです。。 アロエベラは原種名はミラーが名づけたアロエ・バルバデンシズ・ミラーと言いますが、植物学者リンネが名づけたアロエ・ベラ・リンネの方が通称になっています。世界的には栽培種となり、全種がワシントン条約にかかるアロエ属の中でも特例で枠外となっています。 渡来の時期については今から5−600年前という説が有力ですが、伝播の経路としては、現在アロエが自生している地域が、九州、瀬戸内海、伊豆、千葉と主に太平洋側に多く分布していることから、陸路というよりも海路をつたって南から伝わっていったと考えるのが自然と思われます。伊豆でも古くからアロエが自生していたのはここ白浜と南伊豆の一部に限られ、現在見られるキダチアロエの多くは後に植栽されたものと思われます。白浜については15年程前の調査で明治時代に白浜の板戸地区の漁師が持ち込んだという当事者のお孫さんの証言があり、直接の関係者からの情報としてはこれが最も古いものとなります。伊豆白浜地区のアロエの里の名はこの史実に由来しています。日本で自生しているとなると圧倒的にキダチアロエが多いと思われます。キダチアロエは比較的小型で伊豆地方では民家の庭先などでもよく見かけます。化粧品、食品加工された製品となっても、キダチアロエ、アロエベラがほとんどだと思います。 |
<<アロエの特徴>> <形質上の特徴>:  茎・型:大まかに型を分けると、キダチアロエタイプの茎が伸びて木のようになるものと、アロエベラのように地表部で広がり丈の伸びないもの、草のようなグラスアロエといわれると3つのタイプがあります。 茎・型:大まかに型を分けると、キダチアロエタイプの茎が伸びて木のようになるものと、アロエベラのように地表部で広がり丈の伸びないもの、草のようなグラスアロエといわれると3つのタイプがあります。大きさはさまざまで、最小種のディスコイングシーは10cm程度 最大種のバイネシーは20mとアロエの形はかなり多彩です。 一般的に地表茎のものは中〜大型種に多く 地下茎タイプは小型種が多いのが原則です。 葉の形状・色:基本的に三角形で扁平です。 例外として葉先がとがっておらず、まるいカーブを描くプリカティリス 棒状の葉をもつラモシシマなどがあります。 色は基本的に緑色ですが、日本薬局方に掲載されている局方アロエなどは青っぽい葉のものが多くあります。 斑点、縞を持つ種もあり、これまた多彩です。 稀に斑入りのものは観賞用として好まれます。 植物学的には形質に着目して分類を行いますが、アロエの化学的な分析等の研究はの葉部位(全葉)を主として行われているものです。 アロエの花:伊豆に来ると良く見かけるキダチアロエは12-1月に単軸の赤い花をつけます。成熟した株はまれに分岐して二つの花を持ちます。 アロエ属は房に多くの花をつけるのが特徴で一段に15-20程度、2-30段の多段構造ですので、数百の花が一つの花軸についています。 ユリ科の名が示すとおり、筒状の花が原則です。 色は赤、朱系統が多く、アロエベラの場合には5月が最大の開花期でレモンイエローの花軸三叉の花をつけます。 アロエの品種を同定する場合の決め手は花であるほど、各種特徴があります。 私達はアロエの原種保存と観察の目的で、温室を設置し育てています。 カム植物:夜間は気孔を開いて二酸化炭素を吸収して有機酸(リンゴ酸)を生成、日中は気孔を閉じて、夜間生成した有機酸を利用して光合成して糖を作る、普通の植物とは昼夜逆転している植物、 アロエはこのカム植物にあたります。 酸素呼吸をする動物の場合にはクエン酸を使ってエネルギー源を生成しますが、アロエの場合はリンゴ酸。 カム植物は葉に水分を蓄えたものが多いのもこういった代謝システムと関係があるようです。 普通の植物とは異なる光合成システムのため、日中炎天下の水遣りがいけない理由も日中気孔を閉じているアロエの生態に理由があります。 育種:アロエの性質をより高めるため、希少な実生より選抜淘汰を続けたキダチアロエのサラブレッドとなっています。栽培方法についてはさまざま工夫されていますが、アロエそのものの品種改良を行う農家は無く、キダチアロエとアロエベラの自然交配は国内では唯一の成功例です。 今後もアロエの品質向上を目指しています。 |
| [インデックスへ戻る]/[アロエ栽培農園]/[アロエ実験温室]/[製品案内]/[アロエの里]/[お問合せ、ご意見] | |
| <<アロエの育て方・全般>> 育成条件:積雪、霜不可 ■無霜、無積雪、地表の凍結なしならば屋外で可能。 軽く凍結ならダメージはあるものの越冬できる場合があります。 以上の条件を満たさぬ場合、屋外で育てる場合には、鉢植えで、普段はガンガン日を当てて寒冷期だけ室内へ退避しましょう。 最近はミニ温室などもありますが、風通しが悪いと蒸れるので、冬以外は通風の確保を心がけることです。 最近は温暖化の影響か?梅雨時から夏場、風通しの悪い場所ではアブラムシが発生する事があります。 発見したら水道にホースを接続して水流を強くして洗い流してください。徹底的にやった方がいいので、うまく取れない場合には一度鉢から抜いてでもきれいに洗い流しましょう。 食べたりしないのであれば、検疫などでも使用されるマラソンなど除虫剤を指定の濃度で希釈して使用する方法もあります。 その後は風通しの良い場所に置くことで防止効果があります。 ■ 室内でも栽培は可能です。日照、風通しの良い場所ならば良好。 多少日陰気味ですと、ひょろひょろしますが、真っ暗ということでなければ日照不足で枯死ということはないでしょう。アロエはカム植物なので、夜間に室内の二酸化炭素を吸収してくれます。 用土:赤球など(水はけの良い土):腐葉土を 8:2または7:3程度で混合 鉢底に砂利を敷くなどして排水が確保されれば、普通の土や畑の土でもいいようです。アロエの場合栄養過多ですと根が腐るなどのトラブルをお便りいただく事があり、培養土など使う場合には赤玉、鹿沼土など半分くらいいれて、排水を確保し、根が蒸れないよう気遣うとよいでしょう。 一にも二にも排水です! 適した肥料:野菜用や花用の化成肥料でもOK 食べたりするので化成はどうも・・と言う場合は油カスなどの有機肥料をどうぞ。多用は禁物ですので、ひとふり、または数粒で十分です。 個別のトラブルも相談お受けします、お気軽にどうぞ。 植替え時期:アロエも大きくなると鉢を大きくしたり、丈が伸びたら丈を短くしたいなどという事があります。 基本的には通年で植え替え可能ですが、3-5月が最適 オールマイティな植え替えのご説明はこちら 梅雨時や寒冷期には一長一短ですので、こちらをご参考にどうぞ。 株分け:ある程度成長するとキダチアロエ、アロエベラともによく子吹きして、わさわさとしてきます。 基本的に茎から新芽が出てくるので、これを親株から分けて繁殖します。種で・・と思われるかもしれませんが、アロエは乾燥していないと結実しにくく、湿度が高い日本では両アロエとも、ほとんど種は出来ません。 冬季の留意点:冬季、霜、雪がある場合、氷点下になる場合には越冬の留意が必要です。氷点下になる環境では渇水状態にして葉の水分濃度を高くする事によって耐寒性は高くなります。葉が一時的に赤くなったり、葉先が枯れるなどの事はありますが、全体的に葉が残れば、春になれば持ち直して緑が戻るので、凍結させるよりはよいかと思います。 通常室内で越冬させる程度の処置で問題はないかと思いますが、極端な寒冷地の場合には思い切って土から出し、新聞紙などでくるんで、簡易の菰とし、押入れなどで越冬させ、春に植えもどすなどの処置も一計です。 アロエの保水力は半端では無く、数ヶ月無水でも渇水での枯死は通常ありません。 アロエ大好きな楽しみ方(かなりマニアかも^^;) 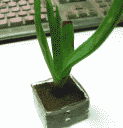 アロエが大好きなのでいつも身近にないとアロエ栽培家は落ち着きません。子株をよく吹くので、ガラス容器に入れてテーブルアロエとしてデスクに置いています。 アロエが大好きなのでいつも身近にないとアロエ栽培家は落ち着きません。子株をよく吹くので、ガラス容器に入れてテーブルアロエとしてデスクに置いています。名づけてアロエ盆栽(笑) 通常の育て方とは全く違います、というか育ちません! 1:ガラス・プラ容器などかわいいものを用意。テーブルに置くので底が抜けていない容器で行います。 2:出来る限り小さな子株(根付)を探す 3:水はけの良い細かい土に挿す。 4:葉がしわしわしてきたら湿る程度給水。これを繰り返す。 留意点:これはアロエベラ1年もの、まったく大きくなりません(笑)半年無水でも生き延びられるアロエならではの楽しみ方です。旅行に出かけるときにも、土が占める程度水を与えておけば1ヶ月でも平気です。さすがだぜ、アロエ! |
<<キダチアロエとアロエベラ>> <補足> アロエとしての特質に配糖体と呼ばれる物質があります。アロエベラとキダチアロエは全体としては含む物質は共通するものが多いのですが、粘性のある糖たんぱく質の質量には違いがあります。アロエには多糖体という高分子の糖タンパク質が含まれますが、アロエベラの方がキダチアロエに比べてはるかに多く含まれています。アロエベラの皮を剥いた時の粘性はこれによるものです。配糖体などの性質には違いがあるようで、成分的にはキダチアロエが固有なものが多く、それぞれに特質があるようです。キダチアロエは加熱に強く、アロエ茶などとして乾燥葉が用いられるのも合理的な理由です。 キダチアロエが苦いというイメージも持たれがちですが、あの苦味の名前はアロエベラの学名アロエ・バルバデンシスに由来しているものです。
|
||||||||
<<アロエの植替え方>> 何故植え替えをするのか?:市販されているアロエは様々な大きさで、5号鉢(直径10cm程度)から8号鉢(直径25cmくらい)のものまで様々です。先述のようにアロエは数mに大きくなる性質のものもあり、アロエベラですら、大きくなれば葉が1m近くまでなる訳で、全重量の90%が水分であるアロエの重さを根が張って支えています。結果ある程度大きくなると地表の部位が重たい性質上、グラグラするとか、鉢から根がはみ出すなどしてくるものです。 根が締め付けられたりするとアロエの生長を阻害したり、妙にひょろ長くなってさらにバランスが悪くなったり、見栄えが悪いなどの問題が出るので、これを回避するために植え替えを行います。 ・さらに大きく育てる ・切り戻して丈を短く大きさをコントロールする。 どちらも可能です。 図解いりでこちら |
<<アロエの株分け・増やし方>> ご家庭で育てられている、キダチアロエやアロエベラは良く子吹きして鉢ので子供がたくさん出てきて窮屈そうになる場合 茎から子吹きしているが、親株を大きく育てたい場合 などに間引きと株分けを行います。 キダチアロエの場合、地表部の茎、及び地上部の茎、どちらからも子吹きして、枝分かれの樹木のように生長します。 アロエの葉を利用する場合など、アロエの葉を大きくするためには、こぶきしたものを間引いたり、分離して挿し木するなどして、親株を大きくしたい事があります。 キダチアロエの株分け:キダチアロエは親株を中心に茎から芽が出ています。 茎の付け根で切除して下さい。切り口は自然に乾燥していきます。特に処置は必要ありません。 枝を残して切ると残った枝に水が溜まって茎が湿度で傷む場合があるので、出来る限り付け根で切りましょう。 親株に水分が集中し、葉の一枚一枚が大きくなります。 水を吸い上げる関係上、多少子株を残しておいた方が良い場合もあります。葉を取りすぎたり、間引きすぎたりしてやしの木のように頭頂部に部にだけ葉が残っている状態の場合、水を吸い上げきれず、茎の途中で折れてしまう場合があります。 が、そこは生命力の強いアロエですので、挿し木で復活するので、極端な事をしなければ特に心配も無いかとは思います。 挿し木にする場合にはある程度の大きさが必要で、茎の付け根からの丈で20cmくらいは欲しいところ、ちびっこな芽でも着根するにはしますけれども、失敗の確立も高いようです。 挿し木の要領はこちら |
||||||||
<<日々の世話・栽培>> 置き場所:日当たりの良い場所、風通しの良い場所 気温・温度管理:霜、積雪などの寒冷以外は屋外で日照を確保 高層マンション、アパードなどベランダに鉢がおけない場合など、日当たりが良く、風通しの良い場所ならば室内でも育ちます。 水遣り:葉に十分に保水しているアロエですので、渇水で枯死することは稀です。天気任せでも渇水で枯死という事はほとんど無いでしょう。 とはいっても鉢植えの場合には、露地に比べて渇水度が高いので多少水遣りに気を遣うと育ちがよくなります。 アロエの水遣りは成長期の夏場が目安となり、太陽の高度が高い日中に水遣りするとアロエの中心部に水が溜まり煮えてしまうトラブルもあるので、夕方鉢が抜ける程度、周囲からかけるのが理想的ですが。午前中早い時間帯でもかまわないでしょう。炎天下に真上から水遣りは控えて下さい。 春秋は3-4日に一度、鉢底から抜ける程度で十分です。(与えすぎて根のトラブルもあるくらいですから)天気任せの方が調子がよかったりすることもあるようですよ。 肥料:野菜用や花用の化成肥料でもOK 食べたりするので化成はどうも・・と言う場合は油カスなどの有機肥料をどうぞ。多用は禁物ですので、ひとふり、または数粒で十分です。 毎年植え替えなどしてやっていれば土が枯れる事はないので過度の肥料は禁物という事で 基本的に過保護にするとダメになるタイプ。見守る心でよく育つアロエです。 補足:アロエの育種 私達はアロエ農家ですので、アロエの個体差に注目し、稀に実生(種から発芽したアロエ)を見つけると農園の片隅でキダチアロエの育種を行っています。より苦い個体、苦くない個体、植物にも個性があるものです。皆さんのよりお役に立てるキダチアロエが出来ればと思っています。 このような農園でアロエを栽培しています。 日本アロエセンター農園 |
<<日々の世話・季節の変わり目>> 私達がアロエを栽培している伊豆白浜は無霜、無積雪、氷点下にならない、ということで 露地でもよく育ちますが、日本国内ではそんな場所は限られているので、季節の変わり目に屋内と屋外を出し入れされておられる方が多いかと思います。 冬場に向けて 気温が5℃を切るあたり、氷点下になる心配がある場合には葉の凍結、根の損傷を防ぐため屋内に入れます。 エアコンや暖房器具の温風の直風は葉がシナシナになる事があるので注意してください。 冬場は水を吸い上げないので、水をあまり与える必要がありません。様子を見ながら与えて下さい。自己の水分で半年も枯死しないアロエですので、無給水でも越冬可能です。多少の渇水状態は室内でも気温が下がる場合などには葉の保水液の濃度が高くなり凍結防止に一助となります。 寒冷気は一時的に葉が赤くなるなどの事がありますが、暖かくなればまた緑が戻るので特に心配はいりません。 この時期は葉先が多少枯れる場合もありますが、外周部の葉はもともと葉先から枯れていずれは落ち、中心部から新しい葉が生えてくるサイクルですから、特に問題ありません。 市場に出回っているものはほとんどが温室など高温栽培で促成してあるものですから、ご家庭での再現は難しく、アロエはその代謝システム上露地で直射日光が適しておりますので、不利な点はありません。 春にかけて 屋内にあったアロエを外に出す時期、暑さ寒さも彼岸までと申します。そのあたりを目安にすればいいでしょう。気温も10度を超えてくれば凍結も無いですし、心配な方は15度くらいの気温を目安にするといいかもしれません。 室内は屋外に比べれば暗いのでアロエは葉緑素を増やして、緑色が濃くなっています。屋外へ出すと葉緑素数の調整と、3月くらいといってもまだ肌寒いこともあり、一時的に風焼けといって、葉が赤茶ける場合があります。本格的に暖かくなれば緑は戻るもので、植え替え時と同じく環境の変化への適応期の減少です。 気になる場合には、徐々に移動して屋外に出していくという方法もあります。小さい株や弱っている株などは、この方法がいいでしょう。 <梅雨時の世話> アロエは保水能力は長けている反面、水分の蒸散機能を犠牲にしているので、意外と多いのが梅雨時のトラブルです。 こちらをご覧下さい。、 |
||||||||
| [インデックスへ戻る]/[アロエ栽培農園]/[アロエ実験温室]/[製品案内]/[アロエの里]/[お問合せ、ご意見] | |||||||||
<<アロエの使い方>> 伊豆白浜では重宝されて、玄関先によく植えられているキダチアロエ、村の細い道をあるけばそこかしこにキダチアロエが見られます。 お年寄りなどは、胃がむかつくと言っては庭にある葉をムシってムシャムシャ食べているのを良く見かけたものです。 寝酒に使うという人もいて、家にはアロエ酒が漬けてあったのも憶えています。 当然のように苦いアロエですが、慣れればどうという事もないという人もいるくらいです。 どちらかというとそういった使い方で日常の食卓にのぼるものという感覚では無いのですが、調理方によってはアロエも美味しく食べられるので、いろいろ試すのも良いでしょう。  これは民宿で作って戴いた撮影用のアロエづくし、アロエは食卓の中の一品でよく、生の葉を食べたり、ジュースで飲む時もお猪口一杯程度で十分なので、 ゼリー質のみの料理でもこれではちょっち食べすぎとなりますが、豪華版で作例をご紹介☆ アロエ生葉使用例などは別途こちらもご参考ください。 保存法・食べ方・手作りアロエ化粧水の作り方など ■アロエ生葉の取り扱いについて |
<食べる> いくつかアロエ料理を紹介したいと思います。 ■Newアロエ料理の基本形:アロエ刺身の作り方  アロエの刺身:魚を3枚におろす要領でアロエの葉のゼリー質のみを取り出すと、ちょうどお魚の切り身のような状態になります。刺身を作ると同じ要領で包丁をいれ、アロエの花を添えてあります。抹茶塩やお醤油で戴きます。 アロエの刺身:魚を3枚におろす要領でアロエの葉のゼリー質のみを取り出すと、ちょうどお魚の切り身のような状態になります。刺身を作ると同じ要領で包丁をいれ、アロエの花を添えてあります。抹茶塩やお醤油で戴きます。キダチアロエの場合には、3枚におろした状態で、沸騰したお湯で湯がくと苦味が収まり、ほのかな大人の味のアロエ刺身となります。粘りもなく、さらっとした食感です。アロエベラの場合には粘性がありますので、キッチンペーパーなどで粘りを吸着させると食べやすくなります。アロエベラの場合、この粘りがいいところなので、もったいないと思う方はどうぞそのまま。ゼリー質だけでも、多量に食べるとお腹が緩くなる事があるので、写真くらいの分量がいいあんばい、食べすぎは注意しましょう。。  てんぷら:日本で栽培しても良く咲くキダチアロエの花を普通のてんぷらの要領で衣につけて天ぷらに、花のみバージョンと葉肉と合わせバージョン てんぷら:日本で栽培しても良く咲くキダチアロエの花を普通のてんぷらの要領で衣につけて天ぷらに、花のみバージョンと葉肉と合わせバージョン葉肉は外皮込みだとほろ苦く、皮むきならたまねぎに似た食感。アロエの花蜜のさわやかな甘さで珍味です。  ステーキ:これはアロエベラバージョン ステーキ:これはアロエベラバージョンサボテンのステーキがあると聞き、アロエでも出来るのではと試したものです。加熱で粘りも飛んで、こんにゃくのようなほくほくした食感、アロエの花を添えました。 思いの他美味しい。  アロエ酢の物:アロエのゼリー質は食感を楽しめるという事で、酢の物 アロエ酢の物:アロエのゼリー質は食感を楽しめるという事で、酢の物海藻類は海の幸豊富な伊豆ですから、海の味、山の味合わせて楽しむことが出来ます。  アロエサラダ:アロエも植物ですから食物繊維も豊富、湯がいた葉肉をサラダにあわせてドレッシングで食べられます。 アロエサラダ:アロエも植物ですから食物繊維も豊富、湯がいた葉肉をサラダにあわせてドレッシングで食べられます。アロエのゼリー質はそのままでは乾燥してしまうので、ラップして冷蔵庫で保冷しておくと作り置き出来て便利、生の場合には透明なうちにどうぞ。時間がたつと多少赤みがかってきます。  手製アロエ茶:キダチアロエの葉を薄く切り、天日で乾燥させ、茶缶などで保管、煎茶の要領でアロエ茶として飲みます。ほろ苦い大人の味、苦味が苦手な方は急須を使って煎茶にひとふり合わせて飲むとまろやか。 手製アロエ茶:キダチアロエの葉を薄く切り、天日で乾燥させ、茶缶などで保管、煎茶の要領でアロエ茶として飲みます。ほろ苦い大人の味、苦味が苦手な方は急須を使って煎茶にひとふり合わせて飲むとまろやか。アロエ薬味:キダチアロエの生葉を2-3cm切り、棘を削ぎ、摩り下ろします。薬味として、お刺身、天ぷらなどに添えます。多量に食べるとお腹が緩くなる事があるので、1-2cmの少量から始めるのがお勧めです。 このように、キダチアロエは苦味剤(調味料)としての側面もあり、10-20g程度をすりおろして薬味としたり、スライスして料理にあわせるなどの利用も可能です。苦味剤として調味料の側面もあるアロエ、日々の生活の中で便利に利用してください。 アロエ利用の際の留意点:多量に摂取するとお腹が緩くなりすぎる事があるので、初めて使う場合には少な目から自分の適量をみつけましょう。 上記の理由で、妊娠中の方、幼児は生アロエの多量摂取は控える方がいいでしょう。 アロエの灰汁(アク)について:ときおり、生のアロエには灰汁(アク)がある、というご質問を受けますが、、アクとは食品においてはエグミやニガミで、アロエの場合には有機酸類及び配糖体、あの苦味が相当します。すべての野菜に含まれているもので、アロエがことさらということはありません。アロエは加工度が高いほど失うものも多く、生のアロエが最も良いというのが定説です。 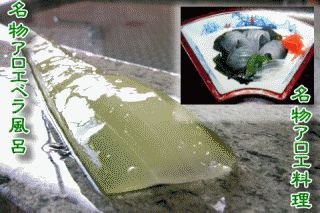 伊豆白浜アロエの里近辺には民宿も多くあり、アロエ風呂・アロエ料理を楽しめる宿もあります。 伊豆白浜アロエの里近辺には民宿も多くあり、アロエ風呂・アロエ料理を楽しめる宿もあります。アロエの葉の取り扱いについては、こちらでも触れているのでご参照下さい。 |
||||||||
| <飲む> 上の写真の左上、アロエジュースです。 キダチアロエ外皮ごとおろして布などで漉したもの。 苦味があるのでハチミツ、レモンで味を調えてあります。 原液ならば個人差はあるもののおちょこ一杯で十分 お酒と相性が良く、このあたりでは漁師さんが二日酔いの翌日になどにアロエを飲んですっきりすると。あの苦味は目も覚めそう。 実際にはお酒飲む前に飲むと良いかと思います。 野菜ジュースとあわせるなどいろいろ使い方を聞きます。 アロエジュースとアロエ酒について作り方をご紹介します。 アロエジュース:はちみつを使って 材料:アロエ生葉・3cm位/はちみつ・おおさじ1杯/水・コップ半分位 1:アロエの生葉をよく洗う 2:3cm程切り、両端のトゲを取る。 3:皮がついたまま大根おろしなどですりおろす 4:3に水とはちみつを加えて出来上がり (氷とレモン汁を加えるとより苦味を感じ難くなります) アロエ酒:材料:アロエ生葉・1kg/ホワイトリカー又は焼酎・1.8リットル/氷砂糖・400g(グラニュー糖等でも可) 1:アロエの生葉1kg分をきれいに洗います。 (乾燥葉利用の場合は25-30g) 2:刺の両端を取り除きます 3:幅2cmほどにカットします 4:広口瓶にカットしたアロエと氷砂糖400g、ホワイトリカー1.8リットルを加えしっかりふたをする。 (注)氷砂糖は飲む場合のみ!手作りヘアトニック、化粧水などとして使う場合には氷砂糖などは入れてはいけません氷砂糖以外にハチミツなど使う場合もあります。味を整えるためですのでお好みで) 5:2−3週間したらアロエは瓶から取り除きます。(取り除かないと濁りや沈殿物が出易くなります。)  → → アロエ原液:アロエの葉3-4cmを切り取り、棘を落としておろしがねなどで摩り下ろします。これを布で漉して、飲みます。 だいたい30cc前後になるはず、アロエは苦味もあり人によって相性もあるので、試す場合には少なめに使ってみるのがお勧めです。 |
|||||||||
<塗る> この辺りでは、アロエの表皮を剥ぎ、葉肉から、出る液を直接肌に塗り付けます、虫刺され、多少の怪我、日焼けのときなどに使用しています。(山に作業に行ったときなどは薬を持っていっていないので) 上記アロエ酒の氷砂糖抜きなどをヘアトニック代わりに使われる方も多いようです。 やけどなどの際にアロエを塗ると良いとある場合がありますが、雑菌の問題があり熱湯消毒して使用するのが適切です。 あくまで薬品では無いので過信は禁物です。 手作りアロエ化粧水:アロエの搾り液や、アロエ酒をベースとして、キッチンペーパーなどで濾過し、精製水、グリセリンなどを合わせ、手作り基礎化粧水とすることもできます。 緑の外葉まで使えばアロエ全開、皮を削いでゼリー質だけ使えばマイルドなベースが出来ます。原液はおろしがねで摩り下ろしたり、ミキサーで粉砕など方法がありますが、いずれも、キッチンペーパーや清潔な布でろ過する事が基本です。 お手製化粧品として使う場合にも、殺菌のため短時間煮沸消毒するのがよいでしょう。 アロエの生葉を屋外でとってきてそのまま使う場合には、お肌につけるものなので、雑菌を防ぐため水や食用洗剤でよく洗う、熱湯をかけて消毒してから使うなどの処置をするのが適切です。 手作り化粧品はパッチテストを必ず行う事をお勧めします。 アロエ生葉の取り扱いについて:アロエ・ベラ手作り化粧水などを紹介しています。 |
<アロエ風呂> アロエを育てていると、子吹きして増えすぎてしまったりする場合もあり、アロエ酒、アロエ風呂などに有効利用することが出来ます。 湯船にアロエを浮かべる時はカスが残るので、循環式の浴槽では布袋、ストッキングなどに入れて使用すると便利です。 キダチアロエ風呂: 材料:キダチアロエの葉、一枚 やり方:棘をそぎ、そのまま湯船に浮かべる。チクチクする場合があるので、その際には皮も加減して剥くと刺激が弱まりまろやかな湯となります。 乾燥葉を用いて代用も可能です。乾燥葉の場合はチクチク感はありません。 生葉重量換算で乾燥葉は約1/20に相当します。 はじめは葉の1/3〜半分くらいを使って試して見ましょう。 アロエベラ風呂: 材料:アロエベラの葉、半分〜一枚 やり方その1:葉のトゲをそいで、湯船に浮かべる。 やり方その2:皮を剥き、ぶつ切りにして野菜ネットに入れる。 湯船で揉みだすとアロエの保湿成分がトロ〜リとしてまろやかな湯となる。 やり方その3:ゼリー質を食したあとの皮をくるくる巻く。湯船に浮かべて漬かる。 アロエベラの粘性は十分に残っているので、結構行けます。 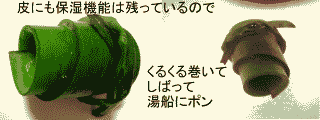 お肌への刺激や、好みによって使い分けてアロエを楽しんでください。 アロエベラの場合など剥いた皮を持て余す場合には無駄なく便利なアロエの利用法でもあります。 |
||||||||
| ■雑談■ ヘアトニックの話;以前先代が畑のアロエを自らヘアケアに使っていたことがテレビに取り上げられ、全国で手作りアロエトニックでヘアケアを試される方が増えました。アロエ酒をヘアケアに使うブーム、発祥の地は伊豆白浜なのです。 |
|||||||||
ぺージトップヘ
最初のページへ戻る
メールはこちらお気軽に
aloe@izu.co.jp
SINCE 21/Sep/1996